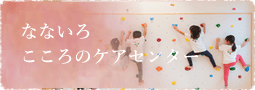- トップ
- コンセプト
なないろの目指すところ
非認知的能力とアタッチメント
いま幼児教育が先進国を中心に見直されています。
2000年にノーベル経済学賞を獲った米国のJ.ヘックマンの研究が端を発しています。どの世代に予算を多く費やせば、国がより効率よく発展するかを検討した研究です。詳細は省きますが、幼児期に非認知的能力である「忍耐力」「自己統制」「自尊心」などの社会的情動スキルを伸ばすことが、より人生の幸福度が高いという結果が出ています(Heckman,2013)。
この非認知的能力を伸ばすために大きな影響を与えるものがアタッチメントです。アタッチメントとは特定の人(母親や父親など)との情緒的な絆です。子どもは乳幼児であっても、どんどん自分の世界を広げていきます。そのなかで母親などの対象にしっかりと守られ受け入れられてこそ、社会との他者との繋がりを持てるのです。対象を「安全基地」としていつでも何かあったら自分を受け入れてくれる場として心の中に存在することで世界を広げ成長できます。
当園では2歳までは、お母さんお父さんとできる限り一緒に過ごしていただくことをお願いしております。親子の絆を、基盤をしっかり作り上げ、園では「我が子のように」一人ひとりを大切に見つめていきたいとおもっています。
先述したヘックマンの研究では、まだまだ議論もなされているところですが、「非認知的能力」を支えたのは、その子どもたちに関わった専門家の質であったとも言われています。あたたかさと良識をもった大人がいつも同じように受け止めそして背中をそっと押していくこと。プログラム云々よりもそのことが大きな要因であったと。
乳幼児期にしっかりとしたアタッチメントを受けた子は、それを一生の糧にします。子どもに関わる専門家としてしっかりと責務の重要さを受け止めていきたいと思っています。
Heckman,J.J 2013 Giving kids a fair chance. Cambridge,MA:MIT Press.
Principal|Nursery teacher
園長 倉俣真理

なないろの大きな特色は保育士と臨床心理士が共に子どもたちの健やかな発達を支えているということです。こころとからだの両面から一人ひとりのお子さまを我が子のように慈しむという思いを大切にしております。それは常に子ども主体であるということ、どんなに幼くても心や思いを持つ「人」として尊重するという観点から成り立っています。
保育園の役割はお子さまを預かる、ということだけではありません。弊園ではお子さまの子育てはお父様お母様が中心となって向き合うことをサポートしています。乳幼児期は、特に母親との関わりはかけがえのないものであり、全ての人間関係はここから生まれると考えています。ご家族の惜しみない愛情が子どもの心を支え、自信をもって社会に飛び立つ力を育ててくれます。ご家族の強い絆があってこそ、お子さまの健やかな成長が保証されると言っても過言ではないでしょう。全てのお子さまの成長の基本はご家庭にあるということをご理解頂けるよう、常にお伝えしています。
もちろん私たち自身の努力も不可欠です。なないろの保育とは、子どもたちの思い、行動の真意を感じ取りながら見守ること。時にはしっかりと導きながら伝えること。何を助け、どこが頑張れるのかを見極めること。たくさん褒め、たくさん抱きしめ、言葉だけでなく、触れ合いや表情の関わりを大切に保育を行っています。
子ども達をより良い環境の中で心豊かに育てるためには、まず私たち自身が保育という仕事を楽しみ、努力し考える姿勢を見せること。子ども達の感性を育むために、私たちが心豊かに接していくこと。そんな姿を見ながら子ども達も力強く育っていくことを望んでいます。
保育目標の「思いやる心」「我慢する力」は保育指針の改定により、ようやく注目され始めた非認知能力に繋がり、人としてベースになる大切な資質です。スタッフ全員が子どもの「こころとからだを育む」という責任の重さを喜びとして日々邁進して参ります。どの子もみんな、我が子のように思いをかけながら。
Vice-Principal |Clinical psychologist
副園長 臨床心理士・公認心理師 笹島京美

子どものこころは個性です。こころは必ず人との関係性のなかで育まれます。スタッフ全員で一人ひとりのこころを大切にみつめながら、メンタライジング(相手が何を思っているかを感じる能力)や感性をご家族とともに育んでまいります。